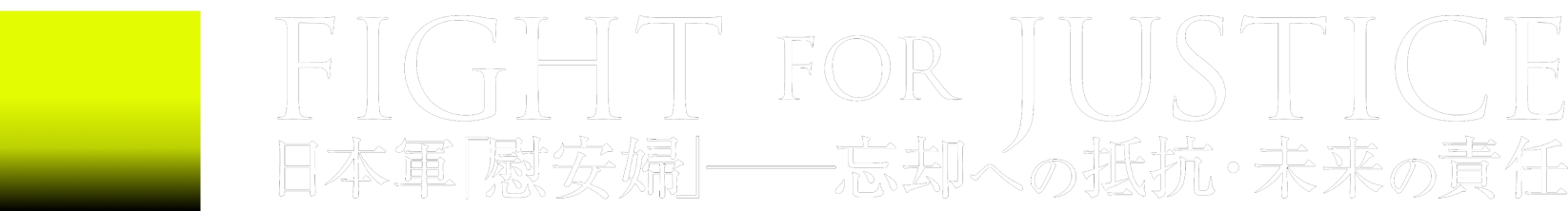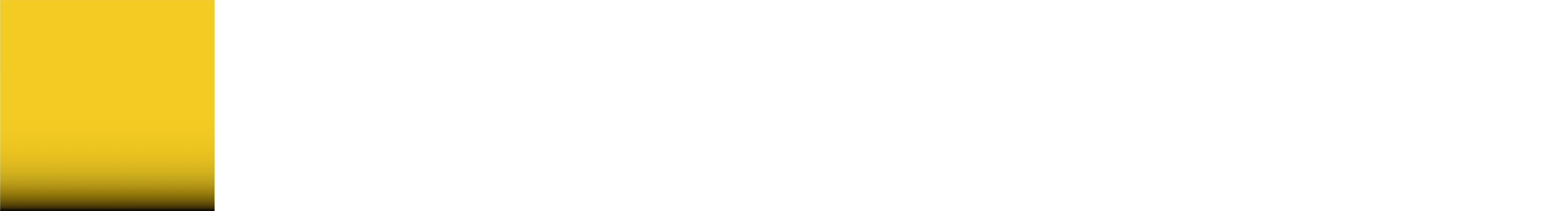日本軍将兵の戦記
明石清三『木更津基地 人肉の市』(洋々社、東京都、一九五七年)五六~五七頁、七七~七八頁。
(著者は朝日新聞記者)
海軍慰安所設置の方針は、航空廠と航空隊の希望とあって、憲兵隊も同調せざるを得なかった。戦争開始以来僅か四ヵ月余、戦地である木更津航空隊と第二海軍航空廠が直面した幾多の現象のうちで、徴用工と召集兵、または職業軍人の性生活の実態は、軍部としては既に満州支那各地の大陸において苦い苦い経験をもっている。木更津は外地の占領地帯ではない。日本内地である。大陸のような方法だけでは解決し得ない。軍民離間の思想が恐ろしい。
〔一九四二年春〕航空廠の一室には、憲兵隊長と総務課長の大佐と常川記者。その他に、常川の計らいで銚子から招かれた売春業者二名が集り、慰安所設置に関する構想が、憲兵隊長から説明されている。
「場所は航空隊及び航空廠から直線三キロを隔てた所で民家の付近を離れること。建物は別紙にあるとおりの二階建三十坪余、十五軒であり、使用の部屋は七つ。三畳を最低とする、夜具用品は特配する、一戸に七人の慰安婦を置いて平均常時百名を維持しなくてはならない。出入箇所に憲兵ボックスを設けて、業者は客の所属階級年令を届出る、この届出には泊りと時間を明らかにし、収支の金額を明示する。衛生用品と用具を備えつける。本年六月下旬までに竣工すること、泊り七円五十銭、時間三円として、超過した場合、業者は直ちに退去を命じられる」
これは命令であった。必要資材は軍資材としてオーダーを発行され、公定価格で買入れが出来る。経営一切及び所有権、その他一切が民間人の企業であって直接軍は関係がない。憲兵ボックスは軍関係の名誉を乱す行為を防止するために設けるもので、売春業者とのつながりはない、などで、責任の全部は業者にあり、軍は一切責めを負わない、と云う虫のいい命令であった。
〔中略〕
しかし、慰安所の建築はなかなか思うように進まなかった。建築資材と熟練大工の労力が不足してママるのが大きな原因だった。 一戸三名と限られ、三名以上を雇入れると超過した女たちは徴用され軍需工場へ送り込まれるという厳命に五十余戸の売春業者は不安な日を送っていた。そうした不安を吹き飛ばすように海軍慰安所進出計画を組合で発表し希望者を募った。これは全員が希望のため組合としても手のつけられないような争いが毎日続いた結果、十五戸を選び第一次六戸が決定した。この六戸は、三人以上七人計十人の傭婦を店におくことが出来ることとなった。慰安所竣工と同時に移動するため待機すると云う理由であった。その六人の業者のうちに朝鮮人の業者がいたため朝鮮娘と沖縄娘が十余名集まってきた。〔中略〕海軍慰安所六戸が竣工して、出入口
に憲兵ボックスが設けられたのは年を越した十八年の二月となってしまった。 脱兎の如く滑り出した建築が、途中で軍側の冷淡から約束の資材の特配が行われず、業者は残りの三分の一は全く自力で闇資材を購入した。大工も闇賃金を出さねば集らなかった。そして六月下旬の竣工が年を越して辛うじて〔一九四三年〕二月に竣工した。〔中略〕 兎にも角にも海軍慰安所が出来上がった。慰安婦たちが待ちかねたように流れ込んできたのは竣工の直後で、一戸に七人から十人が集まり、五十余名となった。
憲兵ボックスには係長である伍長と、部下の兵長の二名が交替で日夜駐留することになり、業者達は恐れをなした。 泊り七円五十銭で、女の手取りは二円五十銭に過ぎない。食費、その他の名称で中間搾取されて仕舞う。
より大きな地図で 慰安所マップ を表示