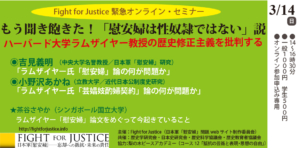雑誌『世界』2022年1・2月号に掲載された対談を全文掲載します(掲載を許可してくださった『世界』編集部に感謝申し上げます)。まず2022年1月号の「上」を掲載します。「下」はこちらからご覧下さい。

歪んだ学知を生み、流通させた構造を読み解きながら、元慰安婦・金学順さんの告発から30年の節目に起きた「事件」の本質に迫る。
はじめに―「知」の全体状況から問い直す
板垣 マーク・ラムザイヤーによる論文「太平洋戦争における性行為契約」に、歴史研究としての手続きの瑕疵と、多くの事実誤認が含まれていることは、『世界』2021年5月号掲載の吉見義明によるファクト・チェックの通りです。先行研究を無視し、史料の扱いも粗雑で、そもそも論文としての体を成していないと一蹴することもできます。
ただ、その前提のうえで、この論文の事実面や手続き面の問題点を訂正するだけでは終わらない構造的な問題についても考えていく必要があると思います。
私自身、『嫌韓流』や日本軍「慰安婦」問題の否定論などに見られる歴史修正主義と多少なりとも対峙してきた経験からしても、内容を学術的に精査し、誤りを指摘するだけでは、十分に対抗しきれないと考えています。もちろん誤りの指摘は不可欠なのですが、批判の運動をつくりあげていくときに、そもそもこうした知識がどのように生み出され(生産)、国境を越えて出回り(流通)、受け止められていくのか(受容)、その構造を踏まえて有効に構える必要があると思っています。なぜこういう論文が出てきて、それがいかなる構造をもっていて、それがどのように受容されていったか―今日はそこを議論できればと思います。
米山 この論文について知ったのは、トロント大学の同僚で朝鮮史研究者のアンドレ・シュミットが転送してくれた抗議活動の声明文からです。北米や英語圏で研究活動する経済学者が中心となって、論文を掲載したInternational Review of Law and Economics(IRLE)誌に対して抗議したものですが、2021年2月の時点で3000を超える署名が、経済学をはじめ、法、歴史、ゲーム理論、アジア研究、学術誌編集に携わる賛同者から寄せられていました。ラムザイヤーの他の論文についても多様な視点から多くの批判があります(ラムザイヤーが過去に発表した論文、抗議声明、署名活動、論考などは以下のサイトで読むことができる。Resources on “Contracting for Sex in the Pacific War” in the International Review of Law and Economics (chwe.net))。
その後、日本でラムザイヤー問題についてコメントを求められる機会がありました。問題となった論文についてはすでに歴史学者から綿密で詳細な検討がされていたので、正直なところ当初は専門家でない私に何か貢献できるのだろうかとも思いましたが、ラムザイヤーの日本に関する議論には、北米、とくに米国で日本についての知が生産されるさいの構造的な問題が凝縮されているとも強く感じていました。批判の広がりの速さや、その多様性にも勇気づけられたこともあって、そのような話をしました。
私自身は戦争や植民地支配をめぐる日米の記憶のポリティクスの問題に取り組むなかで、これをネイションの枠を超えて考える重要性についてくり返し訴えてきました。とくに歴史認識やリドレス(redress:補償)の問題は、太平洋戦争と冷戦が生み出したトランスパシフィックな関係を抜きにしては語れないことを強調してきました。「ラムザイヤー論文事件」は、まさにそのトランスパシフィックな関係をあらためて浮き彫りにしたと考えています。
被害者有責という「理論」?
■ラムザイヤー論文の論法
板垣 ラムザイヤー論文の流通と需要の構造を明らかにするためには、まずこの論文自体の中軸をなす構造を確認しておく必要があると思います。
この論文の中核にあるメッセージは、軍「慰安婦」とされた朝鮮人女性や朝鮮人業者の側に責任や問題があって、日本軍や日本政府には問題がないという点にあります。ただし、それをストレートに言うかわりに、日本軍「慰安婦」制度や公娼制度が、女性と業者の単純な二者間のゲーム理論に当てはめて説明できるという主張を中心に据えた点が、この論文の最大の特徴です。
一般に、ゲーム理論には前提となる人間像があります。それは、それぞれの個人が自分を有利にするための戦略をもっていて、相手の腹を探りあいながら自分の行動を決定するという想定です。その想定のうえでモデルをつくって、どの辺が両者にとっての「最適解」になるかを予想したり説明したりするわけですね。
この論文の基本的な主張は、女性と業者の間に年季奉公契約が成立していて、それが「信頼できるコミットメント」というゲーム理論で説明できるというものです。
つまり、業者が大金を前払いして長期間働かせるが、女性が収入を上げるほど早く足抜けできるようにするという「契約」が、両者の「最適解」として成立している、それで近代日本の公娼制度と日本軍「慰安婦」制度の両方を説明できると主張したわけです。
この論文は、こうしたモデルで説明できると言うために、様々な具体的な歴史的事実を捨象し、多くの事実誤認を犯すことになったわけです。たとえば吉見義明も指摘している通り、史料にもとづき具体的な契約プロセスを検討することなく契約論を展開しているという瑕疵があります。女性個人をとりまく親や親権者、抱え主といった、自由な意思決定を阻害する家父長的な構造もすべて度外視しています。さらに日本軍「慰安婦」についていえば、業者のいわば「元締め」である日本軍の存在が捨象ないし過小評価されています。典型的な、結論ありきの机上の空論です。
ただ、今回問題にしたいのは、この机上の空論自体に明確なメッセージがある点です。日本軍の関与を最小限に見積もることで日本人を免責するとともに、「慰安婦」の被害が末端の朝鮮人業者によるものだとする、典型的な「コリアン有責論」になっています。
■ラムザイヤーの「マイノリティ」論
米山 板垣さんが典型的だとされる「コリアン有責論」ともつながっているのですが、ラムザイヤーが日本を扱った数々の論文の特に深刻な問題として、彼の「マイノリティ」表象や「マイノリティ」観が指摘されています。
被差別部落、在日コリアン、沖縄の基地問題、福島の原発誘致行政などを日本の「マイノリティ」あるいは「下層階級」の事例として提示するのですが、当該コミュニティを取り巻く社会的問題の原因を、政治や社会の主流派に求めるのではなく、被害者や「マイノリティ」とされる側の経済合理的判断にあるとするのが特徴です。地方交付金や行政による福祉や助成、閉ざされた民族コミュニティ内の階層化を利用した暴力的搾取など、被害者や「マイノリティ」であることで生じる(とラムザイヤーが信じる)利益や利権を獲得・保全するべく、不公正を訴える人々が自分の属する集団に対する差別や周縁化を自ら招いている、など。
つまりラムザイヤーの「マイノリティ」議論は、「被害者責任論」だという批判です。
板垣 彼の「慰安婦」論は明らかに、この一連のマイノリティ研究、彼の言葉でいえば「アンダークラス」(下層階級)研究と無関係ではなく、その一環をなすものと見られます。
彼は2018年以降精力的に被差別部落、在日コリアン、沖縄基地問題に関する論文を発表しています。いずれもファクト・レベルでの様々な瑕疵が指摘されていますが、ここで確認したいのは、彼が一連の問題をすべて同じ構図で論じている点です。それがもっとも総合的かつ露骨に表れているのが、“Monitoring Theory of the Underclass”(2020)というディスカッション・ペーパーです。
詳しい説明は省きますが、ラムザイヤーは、ベッカーの「差別の経済学」、パットナムのソーシャル・キャピタル論などを参照しながら、アンダークラス有責論とでもいうべき議論を構築しています。私は読みながら、こうした有名理論の数々を組み合わせてキメラ的なアンダークラス論ができあがることに、率直に驚きました。
この論文のポイントは二つあると思います。一つは、アローの統計的差別論など、もともと雇用主や人事担当者、つまりマジョリティ側の差別のメカニズムを説明しようとしていた理論を、「なぜマイノリティが差別を招きよせるのか」という問いに転換させ、差別の原因がマイノリティ側にあるという話に帰結させた点です。
もう一つは、アンダークラス側に現れるという「機会主義的エリート」(opportunistic elite)に問題の中心を設定した点です。ラムザイヤーは、アンダークラスの「脆弱性」を犯罪率や失業率を指標に定義したうえで(これがまた問題の源泉なのですが)、その「脆弱性」に便乗して「機会主義的エリート」がのさばることになった、と言います。ここで想定されているのは、部落解放同盟や反基地運動などで、この「エリート」がマジョリティに強く迫って利権を得ようとし、かえって差別の境界が維持されてしまう、と主張したわけです。要するにマイノリティ側の反差別運動こそが差別を生み出しているという話です。反差別運動に対するアレルギーに、理論の体裁を与えたようなものですね。
■「タブー」に立ち向かう、という欺瞞
米山 ラムザイヤーは被差別部落を扱った論文で、悪名高い「モイニハン報告書」(1965年)に言及し、報告書を作成したダニエル・パトリック・モイニハンに同情を寄せています。このことはシンガポール大学のティモシー・アモスをはじめとする人々が早くから指摘していた点です。
モイニハンは当時、米民主党政権下の労働省次官補としてこの報告書を作成しました。アフリカ系アメリカ人の貧困の原因がシングル・マザーを長とする黒人家庭にあるとみなし、家父長的で異性愛規範主義的な家庭の建設が貧困の解消に欠かせないとする政策を提言しましたが、被害者だけに責任転嫁して非難していると批判されました。報告書は、貧困を産み出す背景にある奴隷制や、反黒人差別と白人至上主義など、歴史的で構造的な要因を無視しています。にもかかわらず、モイニハンはタブー視されていた問題を指摘したために政治の犠牲となった、と同情を寄せるラムザイヤーのような人々はあとを絶ちません。それは保守や極右に限らず、リベラルで個人主義的な論客の間にも見出すことができます。
逆にこの報告書は、レイシズムが異性愛規範的な家族主義と切り離せないことを示す典型例でもあったので、近年のラディカルな社会運動や研究分野に大きな変化を促してきたクィア・オヴ・カラー批評(queer of color critique)に理論的根拠を与えたとされている点でも重要です。
板垣 関連していえば、“Monitoring Theory of the Underclass”には、実はもう一つ重要な仕掛けが施されています。「機会主義的エリート」論は、単に歴史事象を分析するための概念にとどまらず、この論文の差別性を告発する批判者さえも、その枠組みに押し込めることによって、あらかじめ議論を封じることができる、そういう沈黙効果をもった装置にもなっているのです。これだけ批判を受けても彼が平然としていられるのは、批判を正面から受け止めずに済ませられる機制として、この「理論」が作動しているからではないかとも私は思っています。
米山 「タブーを打ち破る」役割を自らに課すことで、批判を批判として受け止めずに済ますことができるというのはたいへん興味深い指摘です。いわば火中の栗を拾う「率直で勇気ある私」を自作自演することで、己の主張を正当化できてしまうわけですね。
実際には「タブー」とは言えないことなのに、触れてはならない問題であるかのように見せかけ、語れない状況の原因が、反差別運動や「一部の過激派」にあるかのように責任転嫁する……。これは彼に限らず、広くみられる言論状況だといえそうです。同情的なリベラルたちが陥る罠でもあり、トランプ支持者もよく使う仕掛けだと思います。その一方で、イスラエル国家のパレスチナ政策を批判する研究者がしばしば排斥されるといった、「構造的なタブー」については問題視されません。
考えてみれば、金学順さんの証言によって打ち破られるまでは、日本軍慰安所制度の軍事化された性暴力を糾弾することも「構造的なタブー」だったといえます。そもそも「タブー」とは何なのか。「タブー」を産み出す仕組みは何なのか。この罠に陥らないためには、問い方自体をズラしてゆかねばなりません。
板垣 ラムザイヤーは自ら設定した「タブー」に学問的に立ち向かうヒロイックな存在として自身を位置づけ、自らの主張への批判者をもその物語に織り込みました。この言説戦略が、日本軍「慰安婦」問題でも発揮されたわけです。朝鮮人女性や朝鮮人業者に「ゲーム」の責任をなすりつけるとともに、それを批判する言論を「機会主義的エリート」の悪しき所業だと処理できることになります。
この点が明確に現れているのが、Japan Forwardという産経新聞系の英字メディアでのコラムです。そこでラムザイヤーは、まず日本軍「慰安婦」の強制性は純粋なフィクションだと言い切ります。にもかかわらずそのフィクションに固執する団体として、挺対協(韓国挺身隊問題対策協議会、現・正義連)を槍玉にあげます。つまり、挺対協を「機会主義的エリート」として設定したわけです。
彼はさらにそれを「北朝鮮」の存在と結びつけます。正体不明のブログを根拠としながら、挺対協は「もともと韓国の共産主義者によって組織され、韓国政府から北朝鮮関連団体と指定されたこともある」などというデマを公的に反復するのです。そのうえで、「挺対協は韓国と日本のいかなる和解も妨害することで、北朝鮮の政治目的を直接的に推進している」と主張しています。
つまり、日本軍「慰安婦」問題における日本の責任を問う行為は、すべて「機会主義的エリート」のたわごとである、かれらはそこから政治的ないし経済的な利益を得ている、その結果一向に問題が解決しないと、そういうふうに位置づけられたわけです。このようにして「慰安婦」問題がアンダークラス論文と結びつくのですね。
■代理戦争としての「慰安婦」論
板垣 もう一つ見逃せないポイントとしては、彼がこうした日本のマジョリティ擁護/マイノリティ批判を通じて、同時に米国のマジョリティ擁護/マイノリティ批判をしている、ということがありますね。彼は反アファーマティブ・アクション(affirmative action:積極的差別是正措置)論者ですし、その脈絡が、こうした日本論に同時に流れています。
米山 ラムザイヤーは米国には激しい「政治対立(polarization)」があって、人種や民族のポリティクスについての「率直な議論(candid discussion)」は極めて難しいが、日本の社会的差別や「マイノリティ」の事例を用いるなら思い通りの議論が許されるだろう、と論文にはっきりと記しています。米国のアカデミズムの現状に馴染みのある人であれば誰もが注目する点ですね。日本語では「脱植民地化を目指す日米フェミニストネットワーク」の小山エミが『週刊金曜日』(2021年4月22日)で指摘しています。
ひと言でいってしまうなら、ラムザイヤーによる日本の議論は、変容し続けるアメリカに対する不満や苛立ちを日本を語ることを通じて表明するという、いわばトランスナショナルな「腹話術」なのです。北米における日本に関する知の生産という点でとくに興味深いのはこの点です。
ラムザイヤーが「政治対立」と呼ぶのは、90年代以降の「文化戦争(culture wars)」と呼ばれる対立のことです。一般には、共和党政治家パトリック・ビュキャナンがアメリカの信仰と伝統文化のために闘うと宣言したことに端を発しているとされています。その後、社会的少数者のためのアファーマティブ・アクションの撤廃、移民排斥、同性愛結婚の非合法化、市民宗教としてのキリスト教的イコンをはじめとする国家シンボルの普遍化や強制、植民地支配や奴隷制などの歴史の暴力に対するリドレスへの抵抗運動などが促進されました。
つまり「文化戦争」を引き起こしたのは、家父長的で異性愛規範主義的なキリスト教根本主義を中心とするアメリカ白人至上社会の構造や、表象や、知的態度に対する異議申し立てが多くの共感を得ており、大きな広がりを見せていたことに恐れをなした人々による反動だったわけです。その反動の流れは2017年のトランプ政権成立にもつながっています。ただ選挙結果に反映されるか否かとは別に、人種や民族について自由に議論をさせてもらえないと訴えるラムザイヤーのような人々が苛立つ背景には、文化戦争を仕掛けても社会や知のあり方の変化を封じ込められない北米の現状があるのだともいえます。
アファーマティブ・アクションの撤廃をめぐっては、たとえば私が20年近く教鞭をとっていたカリフォルニア州でも、州全体を巻き込む事態に至ったことがあります。公立大学の入学や学資援助の審査に「人種」という差異を持ち出してはならないという州の法律が通過し、その後も抗議活動が続きました。アファーマティブ・アクションは、北米の公共空間から人種やジェンダーなどによって特定の人々が歴史的に排除されたり従属化されてきた結果生じた不公正を(大きな構造は不問に付し)是正しようというリベラルな行政措置にすぎませんが、これが「逆差別」であるとか、差別を助長するといった理由で、保守や極右だけでなく、白人優位の現状や個人主義を肯定する立場の人々からの撤廃要求が起こったという経緯があります。
このように見てくると、ラムザイヤーの日本の「マイノリティ」観と、北米のアファーマティブ・アクションに反対する立場との間に、実に多くの共通点があることがあらためてよくわかります。
要するに、歴史的で構造的な周縁化が社会的弱者や「マイノリティ」を生みだしてきたとする歴史認識を否定したり、社会的不平等や歴史的損傷のリドレスのための施策に対して冷笑的な態度をとるなど、ラムザイヤーの日本版被害者責任論は、北米の「文化戦争」を仕掛けたバックラッシュの動きと、歴史思想的にも社会学的にも、強力につながっているのです。
論文はなぜ流通してしまったのか
■問題のあった掲載誌の対応
―論文の流通を許した米国の状況を問う必要がありますね。
板垣 今回の論文は、2021年1月28日の産経新聞報道をきっかけに国際的に問題が広がったわけですが、そうでなければ今までの論文同様、通常の査読論文として誰もその問題に気づかないまま、素通りされていた可能性があります。
米山 歴史家のテッサ・モーリス―スズキは、「事件」の発端となった論文の杜撰さについて、どんな研究者にも勘違いやミスはあるが、ラムザイヤー論文に関しては誤りや偏りや倫理性に違反している箇所の数が尋常ではないことを指摘しています。この論文を、調査者や研究者の誠実性や、学術論文の基準を満たすために守るべき最低限の原則を学ぶよい例題として提示しているのですが、そのセンスは素晴らしいと思いました。
ではなぜ、これほど明らかに学術論文の基準を満たしていないラムザイヤー論文が、これまで問題なく掲載を許可されてきたのか。誰もが抱く疑問です。最初に述べた経済学者が中心となった抗議文も、掲載誌の査読の経緯や編集者の意思決定を明らかにするよう求めています。
板垣 ラムザイヤー自身、投稿する媒体をある程度選んでいるように見えます。今回の論文は、論争的な内容であるだけに、日本近現代史研究者など、日本軍「慰安婦」問題について多少でも知識や関心がある人が査読すれば、いくらなんでもそのままの形では通らないレベルです。ですから、彼の言う「率直な議論」をしたいと思ったら、日本研究やアジア研究の雑誌では、これは出せません。今回掲載されたIRLE誌は理論モデルが重視される学会誌です。理路整然と書かれていて、モデルの有効性があって、それを裏付けるような「客観的」なエビデンスがあると査読者が説得されてしまえば、わざわざ日本語の資料までさかのぼって検証しようと思わないし、そもそもチェックできる体制になかったのではないでしょうか。
米山 ジャーナルの責任は非常に大きいと思います。単に査読が不十分であったにとどまらず、説明責任という問題もあります。多くの批判が寄せられた後のジャーナルの姿勢は危機管理的というか事故処理的なものでした。
たとえば、Postcolonial Grief: The Afterlives of the Pacific Wars in the Americasなどの著書もある、現カリフォルニア州立大学ノースリッヂ校教員のジナ・キムはこの論文の批判文をオンラインで公表している一人ですが、IRLE誌編集部からラムザイヤー論文への応答文を依頼されて書いた文章を撤回し、掲載拒否した経緯を明かしています(Korea Policy Institute, 2021年2月24日)。キムはその理由を三つ挙げます。
1.反論を依頼する以前にまず自らの責任を果たし、徹底的な再調査を行うべきである。編集者は議論を呼ぶ題材について難しい対話を促そうとしているわけではなく、編集者として本来当然あるべき役割を果たせなかった責任を他の学者に転嫁しているのが実情だ。
2.(自分の反論を掲載することで)アクセス数を増やし、このジャーナルの影響力評価を高める結果を招きたくない。
3.編集部から、ラムザイヤー論文を好意的に評価するコメントも付け加えるよう求められた。論文についての賛否を問うような議論によってラムザイヤーのおぞましい歴史記述の正当化に加担することを望まない。
つまり、ラムザイヤー論文は論争に値するような論点を含むものではなく、「反論」という形がそもそも成り立つ性格のものではないという指摘です。もっというなら、正義や倫理の問題は「賛否」といったフレームで議論されるべきものではない、ということです。
適切な査読をせず、反論を掲載することでバランスをとったとして済ませようというのは、ジャーナルとしての責任放棄だというのが彼女の主張です。このように深く考え抜かれた批判の姿勢には学ぶ点が多くあります。
■問われるディシプリンの立場性
板垣 こうしたジャーナルの姿勢からすれば、その学問分野がもっている倫理観や価値観、さらには人間観(「ホモ・エコノミクス」のような)の政治性も問われる必要があります。
率直に言って、戦時性奴隷制をはじめ、具体的で生々しい人間行為を契約金や契約期間だけでモデル化することなど、そもそもの部分で、私は違和感を禁じ得ません。「慰安婦」問題と特定せず、そういう原理で行動し選択する人が世の中にいるよね、という程度の一般論なら理解しないではありませんが、この人たちはそういう原理で動いていたのだと断ずるのは、とんでもない飛躍と暴力があります。ピエール・ブルデューは、経済理論と経済政策が当然の前提としている人間観それ自体を批判し、社会学の研究対象に組み入れて相対化しましたが(『住宅市場の社会経済学』等)、IRLEなどはそうした研究対象となってしかるべきです。
米山 この雑誌の多くの論文は、経済や商取引に関連する法について、歴史的な事例を引いて理論やモデルを提示するものです。こうした方法論はしばしば、個々の歴史的事実そのものについて軽視する傾向があります。これはこの雑誌に限らず、アメリカの社会科学、なかでもポリティカル・サイエンスやエコノミクス全般に見出される傾向かもしれません。一般にこれらの分野では、普遍的に応用される(と信じられている)ディシプリンで「理論」とみなされるモデルや議論を扱う研究と地域研究とを区別しており、地域研究を劣位に置く傾向があります。地域から得られるのは理論ではなく、データや報道やインフォーマントからの情報で、それは現地のリサーチアシスタントを雇えば収集できると考えられる傾向があります。
もっというなら、普遍的に通用する(と信じられている)概念や理論を重視することじたいが孕む傲慢さについても考えておく必要があります。
今回、かつてのカリフォルニア大学の同僚だった政治学者のチャルマーズ・ジョンソンが、ゲーム理論やその前身ともいえる「合理的選択理論(rational choice theory:RATとも)」が地域研究にもたらす悪影響について懸念していたことを思い出し、あらためて彼の書いたものを読んでみました。「来るべき大惨事―合理的選択理論とアジア研究」(1994年)と題する共著論文で、これは実は、ラムザイヤーが共同執筆した『日本の政治市場』(1993年)の書評です。当時気にも留めていなかったラムザイヤーの名前が出てきたことに、たいへん驚きました。
この共著論文でジョンソンたちは、RAT理論はアメリカの経済的個人や個人主義的合理性を基本としているにもかかわらず、それが通文化的に普遍だという前提を問わないため、地域の歴史や文化を無視し、言語や綿密なフィールド調査を軽視する研究手法を正当化することになる、それはアジア研究にとっての「大惨事」だと警告しています。当然このような研究手法では十分な知識は得られないのですが、説明に矛盾があっても分析モデルの整合性が優先されるため、「事実の改竄や偏向した言い換え」が生じることさえある、と述べています。ラムザイヤーの共著書については、「理論を破綻させないためには、日本でまだ一度も耳にしたことのない慣行を捏造せざるをえない」研究の好例だと酷評しています。何をか言わんや、ですね。
後に改めて触れますが、ここでのジョンソンの「文化」や「伝統」の捉え方は非歴史的で、古典的オリエンタリズムの文化決定論や、アジア特殊論が根底にあります。それでも彼の智力と省察力は確かなもので、ラムザイヤーの論文の数々の問題が見逃されてきた理由が、ディシプリンそのものに共通する問題でもあることに気づかせてくれます。ジャーナルの編集者や査読者たちが、今回の論文も含め、ラムザイヤーの論文の掲載を許してきた背景には、資料や証拠が構築される文脈やプロセスの吟味をなおざりにするディシプリンに特有の研究姿勢や価値観があったといえます。
板垣 確かに、合理的選択理論にせよゲーム理論にせよ、そもそも「モデル」なるものは、立場性が問われなくても済むかのように思わせる装置として機能することもありますからね。自分は「モデル」の妥当性をデータから客観的に判断しているだけだ、という立場に徹することで、そこにどうしようもなく孕まれている立場性に対する評価や判断を避けられるかのように思って、安心しているわけです。
私の経験でいえば、こういう「客観性」の自己神話にひたっている研究者は、だいたい自国のやっていることをおおむね「正しい」もの、「穏健妥当」なものとし、南北朝鮮や在日コリアンや「左翼」とラベリングされた人々からの問題提起を「偏向」と考える人が多いのです。実際は、自らの立場の強烈な政治性を客観視できていないか、そこに居直っているだけなんですけどね。もっともこれは、政治学者や経済学者などだけの問題ではなく、自分は史料を客観的に論じているだけだ、と言って立場性を免除されていると考える歴史学者も同じですが。
■米大学の私有化・国有化
―ラムザイヤーの肩書が「三菱日本法学教授」となっていたことを論文の背景に読み込む人もいます。
米山 大学が内外の企業や政府系団体から寄付金を募って特定分野の研究ポストを作ることは、珍しいことではありません。コミュニティの資産家が寄付金を払って大学に研究ポストを作らせる例もあります。遺族が故人の名前を冠したポストを設けたいという趣旨で行う寄付や、韓国や日本などの政府系団体からの援助で成り立つ教授職も少なくありません。ですから、寄付が必ずしもいわゆる「紐付き」だとは言えません。しかし、寄付によって教員ポストを設けることが、大学の私有化・国有化の一環であることは間違いありません。赴任した人たちがその後のカリキュラム作成や次の新たなポストを決める過程に関わるわけですから、学部の方向性や評価やヴィジョンは大きく左右されることになります。
実は今年、私の所属するトロント大学で、「紐付き」であってはならないはずのポストの人事がスポンサーの介入を受けていた事実が発覚し、北米のアカデミア全体を巻き込む事態にまで至りました。法学部の教員たちが、寄付から成るポストにイスラエルのパレスチナ政策に批判的な研究者を人選していたことがスポンサーに伝わり、大学がこの人事を一方的に覆したのです。学長が権威的な伝手を利用して報告書を作成させ、一連の経緯に問題はなかったと早々に結論付けてしまったことも問題視されました。
カナダ大学教員協会が敏感に反応し、トロント大学が正しい対処をするまで大学主催のイベントや共同研究などへの招聘に応じないよう求める、という協会史上二度目となる非常に重い譴責決議(2021年10月末現在「一時停止」)を行いました。トロント大学の教員たちはSNSやオンライン集会を通じて決議への賛同を求め、ノーム・チョムスキーやナオミ・クラインといった人々からの幅広い支持表明が寄せられました。
トロント大学では、鉱山業で巨額の富を築いたピーター・マンクという資産家の寄付でグローバル・スタディーズ関係のポストなどが潤っていますが、採鉱による環境破壊や世界各地で地元住民と激しく対立してきたことなどから、学生や教員からの批判や抗議が絶えません。与えられたものはよりよい目的のために大いに利用すべきだという人たちもいますが、深刻な社会問題を引き起こしてきた企業や資産家からの寄付を大学が受け取り、見返りとしてそれらの企業名や個人名を教員ポストや建物に掲げたりすることで免罪符を与えてしまう、という懸念があります。
特定企業やスポンサーが研究内容に直接介入せずとも、外部資金が大学という場を歪めてしまう現象は各所で起こっています。ラムザイヤーのポストに三菱の資金が入っているからといって、彼個人の研究が三菱という企業の意向を直接に反映しているとはいえないというのは、手続き上は事実でしょう。しかしハーバード大学の教員たちが、三菱のような経緯を持つ企業からの寄付を容認していること自体が問題なのだともいえます。その意味でも、ラムザイヤー論文事件は北米で再生産されてきた日本に関する知のあり方と切り離しては考えられないのです。
―ラムザイヤー本人の政治信条の問題にとどまらず、論文を生産するディシプリン自体が、中立的な振る舞いでそれを容認してしまっていること、その背景に大学の構造的な問題に横たわっていることが、よくわかりました。
核心は、反アファーマティブ・アクション(「反ポリコレ」と言ってもいいかもしれません)をめぐる、日米の共犯関係にあるようです。歴史的な構造も含めて、この論文がもつ問題の広がりを、後半で深めていただきたいと思います。
(次号につづく)
(2021年6月18日収録。文中敬称略。聞き手=編集部・渕上皓一朗)